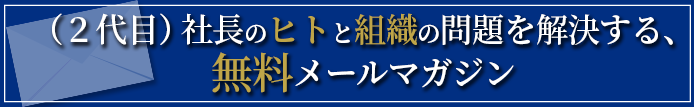第1068号
『人視点』だけで評価制度という
仕組みを作ると、
がんばっているのに賃金が増えない、
という話になることがあります。
2025年、4月22日の日経新聞で
初任給40万円という記事がありました。

評価制度は万能ではありませんが、
評価に賃金が紐づいている以上、
まずは組織全体として利益を出さな
ければならないという『組織の視点』
で作ることが必要です。
———————————————–
社員説明会で、
評価は、よい結果を出せば高い評価
点数をつけますが、賃金や賞与は、
会社の業績に連動します。
昨年より高い点数(評価)であっても、
賃金が同じように上がるわけではあり
ません。
このように伝えても、不満の声は
あがりません。
ですが、いざ昇給や賞与の時期に
なって、評価と処遇が結びつくと
がんばっているのに不公平じゃないか
という声が聞こえてきます。
自分事として実感して、初めて
わかることがあります。
自分の賃金を上げるためには
『全体最適』の視点を
社員の方に持ってもらうことが
必要です。
システム思考という考え方が
あります。
組織全体が最適化され、生産性を
あげることが『全体最適化』です。
具体的には
自分の評価を上げるためだけでなく、
会社の業績と繋がっていることを
意識して成果を出せる行動をする
ことが『全体最適化』です。
一方、
自分は頑張って結果を出しているの
だから、賃金も上がるはずだ、という
のは『部分最適』です。
自分のことに集中しすぎて
周りが見えない状況は、
『部分最適化』と言えます。
社長は「頑張っている人に報いたい、
そんな制度を作りたい」
とおっしゃるのですが、
だからと言って、一部の人だけがんば
ってくれればよいとは思っていません。
願わくば、みんなに頑張ってもらって
報いたい、というのが本当のところ
のはずです。
なぜなら、最大の成果を出すには
一部分の人のがんばりでは達成
できないことをわかっている
からです。
『ザ・ゴール』の著者が開発した
「制約理論」では、
部分最適では、最大の成果には
つながらないと言っています。
評価制度で言えば、
組織の「2:6:2の法則」の
真ん中の6や下の2の向上が
大きく成果を引き上げます。
そのために、評価制度の
評価基準には、
行動できず、立ち止まってしま
ったり、遠回りしている人の
成果を上げる支援をすることを
良しとした、
「優れたやり方を教えている」
という評価基準を入れることが
あります。
再現性があるやり方を
教えられるほど習慣化されて
いることを意図しています。
この評価を得る一番の近道が、
「教える」ことです。

自身の評価シートにこれが
入ることで、
自分だけのことから、必然的に
周りに目がいくことを狙って
います。
最初のきっかけとして
自分の評価を上げるための
方法として取り組むことに
よって
自分に向けた努力だけでは
昇給、賞与の額を上げられ
ないけれど

全体最適を目指して、
組織に目を向けて、
組織の成果に貢献する
ようになると、
個人の最適、すなわち
自分の賃金が上がるという
「部分最適」も可能になる
ということに、気づくことが
できるというものです。
そのためにも、制度設計は
賞与や昇給には、
人件費の原資の額によって
決められていて
その額は、業績や粗利に連動して
いるということを明文化したうえで、
実際にそれを実行していくことで
社員の方は組織の視点を持つ
ようになっていくのだと思います。
お読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
このブログは、メルマガでも平日2回
お届けしています。
ご希望の方は、 下記フォームよりご登録ください。