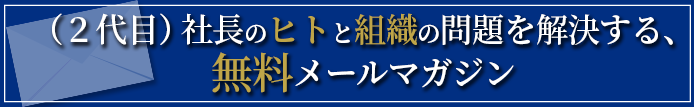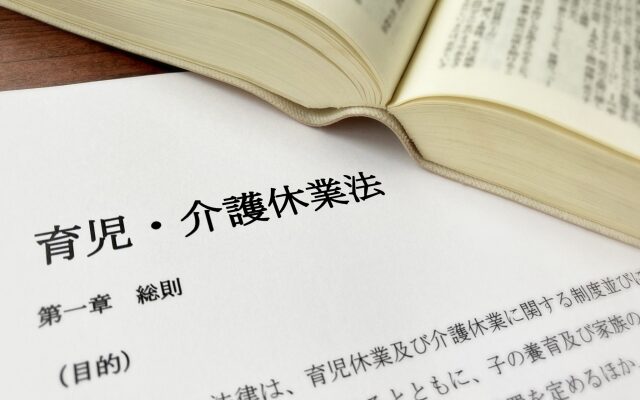
第1067号
毎年、労働法関連の法改正があることを
ご承知の方も多いと思います。
実務で考えると、私もそうなんですが、
規程を変えて、届出して終了気分に
なってしまいます。
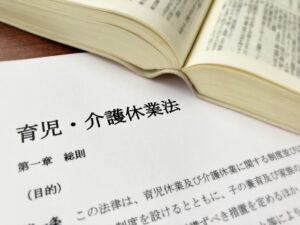
でも、法改正のねらいを考えると、その後の
運用を真剣に考えなければと思わされます。
求められているのは会社の構造の変化です。
————————————————–
「現状」の視点にたてば、
リスクヘッジとして規程を改訂する
ことでよいと思うのですが、
会社として今後の組織づくりの方向性
という「未来」を見据えると
規定した後の組織の運用を考えない
わけにはいきません。
最近、一番大きくとりあげられているのは
育児介護休業法です。
育児介護休業法以外にも法改正が
あるので、総務、人事は大変です。
さて、2025年4月の改正では
厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
3歳未満の子を持つ労働者や介護している
労働者にテレワークが『努力義務』
とされました。

ワークライフバランスの実現や
生産性の向上促進
そして育児休業法で考えると、
少子化対策でもあります。
女性にやさしい職場という表現
を求人などで目にすることがあり
ますが、もはや男女の区別はあり
ません。
育児休業は男女共に取得できるもの
として、認知していかなければならない
ことです。
育児休業取得状況の公表義務が
300人超の企業に引き下げられた
ことからも、
会社の意識を変えて、真剣に取得
できる環境づくりを、国はますます
促してくるものと感じます。
3歳未満の子を養育する労働者が
テレワークを選択できるように
措置を講ずることが『努力義務』
となったことは、

これまで努力義務が、いずれ義務化
されてきた流れを考えると、
テレワークはうちの会社ではできない、
とも言っていられなくなりそうです。
会社の声を聞いてみると
少し前までは、育児休業取得者が
複数重なると、業務を回すのが
厳しいという声だったのが、
今は、人手不足をやりくりしてでも
辞めずに復帰してほしい、という
ように、変わってきたことを感じます。
それほど、人材確保が難しい
状況なことがわかります。
こうした時代の変化が、会社の意識
を変えた、と言えます。
それでも、まだまだ誰かの頑張りの
上にようやく成り立っている状況です。
社会保険労務士の多くの方が
4月より10月の法改正の運用が
難しいとおっしゃいます。
・柔軟な働き方を実現するための措置等
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
なかでも、個別の意向聴取・配慮は
・労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時
・子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間適切な 時期
(柔軟な働き方を実現 するため及び仕事と育児の両立について)
2回、確認することが盛り込まれています。
労働者とコミュニケーションをとって
労働者が自分の意思で適切に
選択してもらうことが狙いです。
ですから、労働者とよくコミュニケーション
をとることは、確かに大切です。
でも、私はその前に
柔軟な働き方を受け入れられる
組織風土になっているかどうかが
問われているんだと感じます。

柔軟な働き方として、5つ挙げられ
た中から会社ごとに2つ選んで
規定化して、
どれを選ぶか決めてもらう、
というのが規程作成の流れですが、
2つ選べる会社はよいのですが、
実際のところ、選べない会社も
出てくるだろうと思います。
個別の意向聴取をしても、配慮が
十分にできない事案も出てくる可能
性もあります。
労働者に利用を控えさせるような
後ろ向きな対応にならないように
不公平感や不満を少しでも小さく
して、労働者と折り合いをつけら
れるコミュニケーションをとるためにも
時代の変化のスピードによって起こる
様々な組織の問題を“全体最適”で
判断して解決していくことが先決です。
解決方法は、会社ごとの状況に
よっても、取り組む内容や順番が
違います。
働き方改革、同一労働同一賃金の
ときがそうだったように、
今年の法改正も、そしてこれからの
法改正も、
人事や総務の仕事の域を超えて
経営者に、自社のボトルネックを
解消して “全体最適” の視点で改善に
取り組むことを、求められていくのだ
と思います。
お読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
このブログは、メルマガでも平日2回
お届けしています。
ご希望の方は、 下記フォームよりご登録ください。